──「いいモノ」を“適正価格”で届けるために
「売れるアイテム」ではなく、「売れ続ける売り場」を考えたことはありますか?
ただ安いビジネスも続かないですし、ファンからひたすら集金するビジネスも続きません。続けるにはどうしたらいいか。この記事で考えていきます。
この記事でわかること
- 利益率・原価率を “パーセント” で考える理由
- 原価率○%が目安と言われる根拠と下げ方
- 「単価 × 数量 × 品質」の三すくみ をどう解決するか
- 具体的アクション ⇒ 「グッズをつくる」「デザインをつくる」「販売する」3つのステップ別記事へジャンプ
こんな人におすすめ
- 物販は初挑戦、でも価格設定だけは外したくない
- 「限定販売」でも黒字にしたい副業クリエイター
- 客単価と在庫リスクを同時に改善したいブランド担当者
1. 利益は“円”ではなく“%”で見る
販売価格が違う商品を横並びで判断するには 率(パーセント) が必須。
| 商品 | 原価 | 販売価格 | 利益 | 利益率 | 原価率 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | ¥ 1,000 | ¥ 3,000 | ¥ 2,000 | 66% | 33% |
| B | ¥ 2,000 | ¥ 3,000 | ¥ 1,000 | 33% | 66% |
| C | ¥ 1,500 | ¥ 10,000 | ¥ 8,500 | 85% | 15% |
利益率(%) = 利益 ÷ 販売価格 × 100
原価率(%) = 100 − 利益率
2. 原価率 30〜40% が“定番商品”の目安
- 見込み生産(在庫リスク高) … 30 %前後 に抑えると健全
- 受注/限定販売(在庫リスク低) … 60 %までOK
初めての物販は原価率 60%でも許容 → まず“在庫ゼロ”で客層を計測し、
売れる確度が見えたら数量をまとめて原価率を落とす のが王道。
3. 原価率を下げる 3 つの方法
| やり方 | 具体策 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| ① 販売価格を上げる | ¥ 500 → ¥ 1,000 | 原価率即改善 | “高すぎ”で離脱の危険 |
| ② 品質を落とす | 生地厚7oz → 5oz | コストカット大 | ブランド価値低下 |
| ③ 生産数量を増やす | 10 → 100 枚 | スケールメリット | 在庫リスク増 |
高単価 × 少客層 か 低単価 × 多客層 か――どちらで行くかは「ブランド戦略」で決める。
【ケーススタディ】生産数量による利益差
キーホルダー 販売価格 ¥ 1,000/個、その他コスト除く
販売数:300個 売上:¥ 300,000
| 1回生産数 | 1個原価 | 300個売れた場合の総利益* |
|---|---|---|
| 1 枚 × 300回 | ¥ 500 | ¥ 150,000 |
| 50 枚 × 6回 | ¥ 400 | ¥ 180,000 |
| 100 枚 × 3回 | ¥ 350 | ¥ 195,000 |
| 300 枚 × 1回 | ¥ 300 | ¥ 210,000 |
同じ販売数でも 受注まとめ×ロット割引 で利益が 30 万円近く変わる。
4. “単発グッズ”ではブランド価値が上がらない
- 1個だけ作る ⇒ 話題になりにくい/再販も読めない
- “まとめて10セット”+ストーリー がある ⇒ SNSで語られる・追加発注しやすい
💡 解決:ステップ別に考える
| ステップ | 課題 | 今読むべき記事 |
|---|---|---|
| デザインを作る | アイコン・ロゴが未整備 | 🔗 生成AI時代の“実務ツール”はどれ?結論、Fireflyを触っておくと得をする |
| グッズを作る | 小ロットで試したい | 🔗 10セットでOK!小ロットでカルチャーグッズを作ろう |
| 販売する | 欲しいと言われた後どう売る? | 🔗 AI時代に「自分のEC」を持つ選択をする |
5. 商品ラインナップで利益率を底上げする
- A商品:利益高・需要中
- B商品:利益低・需要高
- C商品:利益中・需要低
「売れる物に追加投資、売れない物は値下げで現金化」
⇒ プロジェクト全体で 平均利益率 40%超 を狙う。
6. まとめ ── “適正価格 × 適正数量 × 適正品質”
- 率で考えれば意思決定が早い
- 在庫リスクを抑えて客層を測る → 数量をまとめて原価率を落とす
- ストーリー付きの小ロット でブランド価値と利益を両立
どんな人にどんな物を、そしてどんなストーリーを届けたいか。ブランド軸をぶらさずに、意思決定を速く微調整続けていくことで、ブランドビジネスを長く続けていきましょう。
販売グッズをつくる次の一手
最後に余談
クリエイターやインフルエンサーが「作りたいものを作る」のは素敵です。
ただ、“長期計画で物販を設計” できれば、もっとファンに喜ばれ、あなた自身も続けやすくなります。
時間がない? なら パートナー と組めばいい。
コンテンツ初期から物販の視点を入れて、ファンと一緒に“買い支える文化”を育ててみませんか。
そんな方をささきや商店はアシストします。

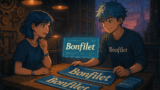



Comment